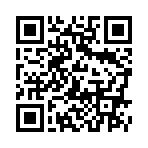2012年02月29日
食の文化祭
今回の「鬼無里」情報は、“食の文化祭”
食文化を学んで、どんな『うんまいもの(美味しいもの)』が頂けるかワクワクしながら、国道406号線を行く。 。場所は鬼無里活性化センター(鬼無里支所のとなり)。中に入ると、入り口には鬼無里の名物がずらりと並び、今回は何を買おうかと物色していると、「ソノマノ」のパンが出店されていた。一も二もなく早速購入。このパンは以前、「いいときいろどり」で紹介。→「職人のパン」
。場所は鬼無里活性化センター(鬼無里支所のとなり)。中に入ると、入り口には鬼無里の名物がずらりと並び、今回は何を買おうかと物色していると、「ソノマノ」のパンが出店されていた。一も二もなく早速購入。このパンは以前、「いいときいろどり」で紹介。→「職人のパン」

さて・・・本題に戻ると
この「食の文化祭」は四季を通じて年4回の企画で、今回のテーマは『冬』
会場には、80名ほどの参加者で満席状態
なんと長野駅からの直行便が出たほどの人気
 食と行事は関連が深いもの。まずは鬼無里の冬の行事を映像で学びます。
食と行事は関連が深いもの。まずは鬼無里の冬の行事を映像で学びます。

14ほどの冬の行事の紹介が終わると、「いいてんきだぁ~ね~」と県農村文化協会の池田玲子さんの講話が始まった。

ここの鬼無里には「さがみっちょ=良いリーダー」が大勢いるのが魅力なんだわ。こんな山深い土地に住み続けられるわけは何か?そりゃ先人から受け継いでいる『食いつないでいく、という知恵と技』なんだよ。夏は冬に備えて、冬は夏への準備と、生きていくっていうのは大変。」と語る。そして、
「鬼無里が大切にしてきた“祈り” “願い” “感謝”の心を感じて、用意されている郷土料理を食べてもらいたいわ。」と続けた。最後に、「ここの土地のものを食ってりゃ命を保証するよ、その代り大変な時は手伝ってくれやな、という関係づくりを築きたいんだよ」と締めくくった。「恩恵に与かる」という言葉が頭に浮かんだ。「恵み」にかかわりをもつ。関与する。ということなのだ・・・きっと。
こんなありがたい気持ちを噛みしめていると、試食会場へ80名の大移動が始まった。後れを取ってはいけないっ!と人の間をかいくぐり ・・・会場に入ると、圧巻だった。まずは、ご用意いただいたお料理を見ていただきたい。(写真をクリックしてね。拡大でご覧になれます。)
・・・会場に入ると、圧巻だった。まずは、ご用意いただいたお料理を見ていただきたい。(写真をクリックしてね。拡大でご覧になれます。)
主催者の方から作り方など説明を受け、さあ!試食タイム


中でも、なすの寒干し炒めはステーキと間違えるくらいと大好評。(県知事もまちがえたらしい )
)
おや?向こうのコーナーでは可愛らしい割烹着を着た小学生たちが「そばクレープ」の実演を始めた。


実演しているのは、鬼無里小学校3年生7名の皆さん。自分たちでそばを栽培して石臼で挽いた100%鬼無里産のそば粉を使ってご馳走してくれた。トッピングも土地のものを使った「ネギ味噌」で本当においしい。
たくさんの知恵と技が生きた、お料理を堪能した後は、長野県短期大学の皆さんによるお勉強会 会場入り口に用意されたペットボトルに入った水の飲み比べだ。
会場入り口に用意されたペットボトルに入った水の飲み比べだ。

用意されたのは、鬼無里の3地区の原水と長野市の水道水。水道水を当てるクイズだが、果たして参加者の舌は・・・
正解した方がたくさんいて、まだまだみんなの舌もまんざらじゃない!
県短の中澤先生は、「食について考えるとき、水は欠かせないもの。その水を見直してもらうための第一歩として、水の飲み比べをした。天然水は丸みのある優しい味がするという違いについて、認識していただけたのは大きい」という。
綺麗で美味しい自然の水こそが「宝物」。そして、これがすべてに波及していくのだろう。
鬼無里の自然・歴史・文化を大切にし、「食」の未来を考えたい。
次回が楽しみです。
続きを読む
食文化を学んで、どんな『うんまいもの(美味しいもの)』が頂けるかワクワクしながら、国道406号線を行く。
 。場所は鬼無里活性化センター(鬼無里支所のとなり)。中に入ると、入り口には鬼無里の名物がずらりと並び、今回は何を買おうかと物色していると、「ソノマノ」のパンが出店されていた。一も二もなく早速購入。このパンは以前、「いいときいろどり」で紹介。→「職人のパン」
。場所は鬼無里活性化センター(鬼無里支所のとなり)。中に入ると、入り口には鬼無里の名物がずらりと並び、今回は何を買おうかと物色していると、「ソノマノ」のパンが出店されていた。一も二もなく早速購入。このパンは以前、「いいときいろどり」で紹介。→「職人のパン」
さて・・・本題に戻ると

この「食の文化祭」は四季を通じて年4回の企画で、今回のテーマは『冬』
会場には、80名ほどの参加者で満席状態

なんと長野駅からの直行便が出たほどの人気

 食と行事は関連が深いもの。まずは鬼無里の冬の行事を映像で学びます。
食と行事は関連が深いもの。まずは鬼無里の冬の行事を映像で学びます。
14ほどの冬の行事の紹介が終わると、「いいてんきだぁ~ね~」と県農村文化協会の池田玲子さんの講話が始まった。

ここの鬼無里には「さがみっちょ=良いリーダー」が大勢いるのが魅力なんだわ。こんな山深い土地に住み続けられるわけは何か?そりゃ先人から受け継いでいる『食いつないでいく、という知恵と技』なんだよ。夏は冬に備えて、冬は夏への準備と、生きていくっていうのは大変。」と語る。そして、
「鬼無里が大切にしてきた“祈り” “願い” “感謝”の心を感じて、用意されている郷土料理を食べてもらいたいわ。」と続けた。最後に、「ここの土地のものを食ってりゃ命を保証するよ、その代り大変な時は手伝ってくれやな、という関係づくりを築きたいんだよ」と締めくくった。「恩恵に与かる」という言葉が頭に浮かんだ。「恵み」にかかわりをもつ。関与する。ということなのだ・・・きっと。
こんなありがたい気持ちを噛みしめていると、試食会場へ80名の大移動が始まった。後れを取ってはいけないっ!と人の間をかいくぐり
 ・・・会場に入ると、圧巻だった。まずは、ご用意いただいたお料理を見ていただきたい。(写真をクリックしてね。拡大でご覧になれます。)
・・・会場に入ると、圧巻だった。まずは、ご用意いただいたお料理を見ていただきたい。(写真をクリックしてね。拡大でご覧になれます。)主催者の方から作り方など説明を受け、さあ!試食タイム



中でも、なすの寒干し炒めはステーキと間違えるくらいと大好評。(県知事もまちがえたらしい
 )
)おや?向こうのコーナーでは可愛らしい割烹着を着た小学生たちが「そばクレープ」の実演を始めた。


実演しているのは、鬼無里小学校3年生7名の皆さん。自分たちでそばを栽培して石臼で挽いた100%鬼無里産のそば粉を使ってご馳走してくれた。トッピングも土地のものを使った「ネギ味噌」で本当においしい。
たくさんの知恵と技が生きた、お料理を堪能した後は、長野県短期大学の皆さんによるお勉強会
 会場入り口に用意されたペットボトルに入った水の飲み比べだ。
会場入り口に用意されたペットボトルに入った水の飲み比べだ。
用意されたのは、鬼無里の3地区の原水と長野市の水道水。水道水を当てるクイズだが、果たして参加者の舌は・・・
正解した方がたくさんいて、まだまだみんなの舌もまんざらじゃない!
県短の中澤先生は、「食について考えるとき、水は欠かせないもの。その水を見直してもらうための第一歩として、水の飲み比べをした。天然水は丸みのある優しい味がするという違いについて、認識していただけたのは大きい」という。
綺麗で美味しい自然の水こそが「宝物」。そして、これがすべてに波及していくのだろう。
鬼無里の自然・歴史・文化を大切にし、「食」の未来を考えたい。
次回が楽しみです。
続きを読む