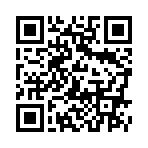2012年11月29日
本格的なコーヒーが楽しめる!エルム
市街地からループ橋を上って、飯綱高原スキー場に突きあたり、右に進んで行くと・・・
“珈琲”と書かれた看板を発見♪


エルムさんは飯綱高原の東、「長野県環境保全研究所」の近くにあります。
今日はこちらでコーヒーブレイクです。

 メニューを見ると気になるお料理がたくさん。
メニューを見ると気になるお料理がたくさん。
前言撤回!コーヒーブレイクではなくランチタイムに変更♪
注文したのは、ポークカレー。レギュラーサイズで¥700。
 レギュラーサイズでもボリューム満点
レギュラーサイズでもボリューム満点
ピリ辛のカレーは、この時期身体の中からあったまります。


↑こちらはケーキセット。
コーヒーが付いて¥580は、とってもお得
手造りシフォンケーキには生クリームとアイスものっていました♪
コーヒーは本格的なサイフォン式で香りがよく、このほろ苦さがケーキとの相性ばっちり。
デザートをいただいた後ですが ・・・ 気付いちゃったんです!
気になるメニュー。〝手造りみそ田楽〟2本で¥250。
 群馬出身のオーナーが手造りした本場の“こんにゃく”。
群馬出身のオーナーが手造りした本場の“こんにゃく”。
市販の“こんにゃく”とはプリプリ感がちがいます。
家庭的なお味にほっこりしながら、気さくなオーナーとのおしゃべり・・
お店はアットホームな雰囲気に包まれていました(´∀`○)
場所:長野市北郷2050-208
定休日:火曜日・第一月曜日(12~3月は月・火・水曜日と木曜日13時まで休み)
営業時間:11時~20時
駐車場:店舗前6台、店舗裏にも駐車可能スペース有
詳しくはこちらをクリック→エルム
信越高原連絡協議会のお得な割引券
わくわく割引チケット利用可(ソフトドリンクが100円引)
“珈琲”と書かれた看板を発見♪


エルムさんは飯綱高原の東、「長野県環境保全研究所」の近くにあります。
今日はこちらでコーヒーブレイクです。


前言撤回!コーヒーブレイクではなくランチタイムに変更♪
注文したのは、ポークカレー。レギュラーサイズで¥700。


ピリ辛のカレーは、この時期身体の中からあったまります。


↑こちらはケーキセット。
コーヒーが付いて¥580は、とってもお得

手造りシフォンケーキには生クリームとアイスものっていました♪
コーヒーは本格的なサイフォン式で香りがよく、このほろ苦さがケーキとの相性ばっちり。
デザートをいただいた後ですが ・・・ 気付いちゃったんです!
気になるメニュー。〝手造りみそ田楽〟2本で¥250。

市販の“こんにゃく”とはプリプリ感がちがいます。
家庭的なお味にほっこりしながら、気さくなオーナーとのおしゃべり・・
お店はアットホームな雰囲気に包まれていました(´∀`○)
場所:長野市北郷2050-208
定休日:火曜日・第一月曜日(12~3月は月・火・水曜日と木曜日13時まで休み)
営業時間:11時~20時
駐車場:店舗前6台、店舗裏にも駐車可能スペース有
詳しくはこちらをクリック→エルム
信越高原連絡協議会のお得な割引券
わくわく割引チケット利用可(ソフトドリンクが100円引)
2012年11月26日
ウィンターシーズン到来!「戸隠スキー場」
戸隠スキー場にも雪が積もりました

いよいよスキーシーズンの到来です!
そこで「魔法の粉雪」で有名な戸隠スキー場のオープン情報をお伝えします。
戸隠スキー場 2012-2013シーズン
12月15日(土)オープン~4月14日(日)予定
12月15日~21日は〝初滑りキャンペーン〟となっており、リフト料金がお得に
またシーズン券が12月9日受付分まで早割が適用されます!
シーズン券をお求めの方はお早目にお求め下さい。
シーズン券情報はこちらをクリック→
お問い合わせは、戸隠スキー場
電話:026-254-2106
詳しくはこちらまで↓
HP:http://togakusi.com/


撮影日11月14日
いよいよスキーシーズンの到来です!
そこで「魔法の粉雪」で有名な戸隠スキー場のオープン情報をお伝えします。
戸隠スキー場 2012-2013シーズン
12月15日(土)オープン~4月14日(日)予定
12月15日~21日は〝初滑りキャンペーン〟となっており、リフト料金がお得に

またシーズン券が12月9日受付分まで早割が適用されます!
シーズン券をお求めの方はお早目にお求め下さい。
シーズン券情報はこちらをクリック→

お問い合わせは、戸隠スキー場
電話:026-254-2106
詳しくはこちらまで↓
HP:http://togakusi.com/
2012年11月22日
いいとき人物譚 村田幸恵さんの記事を公開!
いいときナビのコンテンツ「いいとき人物譚」に新しい記事が加わりましたのでご紹介いたします!
いいとき人物譚では、「生まれも育ちもいいとき」、「いいときエリアで働いて○○年」という方々から地元ならではの視点でいいときの魅力を語っていただきます。

今回は、戸隠登山ガイド組合で数少ない女性ガイドとして活躍する村田幸恵さんにお話を伺いました。
戸隠生まれで、戸隠を熟知していている村田さんが語る、「戸隠を歩く魅力」や「もうすぐ訪れる冬の楽しみ方」をぜひご覧ください。
いいときナビ いいとき人物譚
「荘厳な雰囲気のある場所 戸隠」 村田幸恵さん

【オニグルミの冬芽の観察】
村田さんが教えてくれた戸隠の冬ならではの楽しみ方「冬芽の観察」
いいとき人物譚では、「生まれも育ちもいいとき」、「いいときエリアで働いて○○年」という方々から地元ならではの視点でいいときの魅力を語っていただきます。
今回は、戸隠登山ガイド組合で数少ない女性ガイドとして活躍する村田幸恵さんにお話を伺いました。
戸隠生まれで、戸隠を熟知していている村田さんが語る、「戸隠を歩く魅力」や「もうすぐ訪れる冬の楽しみ方」をぜひご覧ください。
いいときナビ いいとき人物譚
「荘厳な雰囲気のある場所 戸隠」 村田幸恵さん

【オニグルミの冬芽の観察】
村田さんが教えてくれた戸隠の冬ならではの楽しみ方「冬芽の観察」
2012年11月21日
戸隠古道を行く!!その30 「奥社」
「九頭龍社」の右手にある階段を上ると、

戸隠古道の最終地点。

奥 社
戸隠山の大岩壁の真下とも言える場所に建つ「奥社」は、戸隠神社の本社です。
嘉祥2年(849年)学問行者が道場として開いた戸隠寺が起源と言われているようです。
古くは戸隠三十三窟の岩窟の中にあり、第一本窟が奥社本殿だったと言われています。

「奥社」は、日本神話にある「天照大神」が天の岩屋にお隠れになった時、無双の神力をもって、天の岩戸をお開きになった「天手力男命」を戸隠山の麓に奉斎した事に始まります。
戸隠神社の御本社として全国に開運、心願成就、五穀豊熟、スポーツ必勝などの御神徳が広宣され多くの崇敬者が登拝されます。

かつて奥社社務所に籠る役は、本院燈明役(とうみょうやく)と言われ、衆徒(寺の僧徒のこと)が2年交代で務め、事故がない限り下山できないほど重要なお勤めとされてきたらしい。
俗世間から切り離されたこの秘境での修行を思うと、言葉では伝えられない壮絶さが想像されます。
「奥社」から空を見上げると、切り立った岸壁の戸隠山が迫ってくるように感じます。

今日のように青空に“凛”と立つ戸隠山を背にした「奥社」は本当に見事で美しい。しかし、季節はまもなく「冬」。この切り立った岩璧から吹き降ろす雪と風に耐えなくてはなりません。
そんな自然の摂理を思うと、あの詩を思い出します。
ここで、「戸隠古道」の旅は終わりとなります。
「一の鳥居」から「奥社」までは、やはり長い道のりでした。「修行」などと大それたものではありませんが、石柱が立つ戸隠由縁の地を一つ一つ丁寧に周りながら、その場所に伝わる話に耳を傾けていると、自然と古の人たちの声が聞こえてくるようでした。
そして、その声に今の自分を重ねながら歩いた「戸隠古道」はとても楽しい時間となりました。
ぜひ、みなさんも四季折々にいろんな表情を見せてくれる自然豊かなこの道を、ゆっくりと時間をかけて歩かれたらいかがでしょうか。
さて、読者の皆様には大変お世話になりましたが、この記事をもって、私、堀内は筆を置かせていただくこととなりました。
約一年という短い間でしたが、充実した時を過ごさせていただきました。
今後は後任の高橋が、皆様にいいときエリアの旬な情報をお届けいたしますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
本当にありがとうございました。

戸隠古道の最終地点。

奥 社
戸隠山の大岩壁の真下とも言える場所に建つ「奥社」は、戸隠神社の本社です。
嘉祥2年(849年)学問行者が道場として開いた戸隠寺が起源と言われているようです。
古くは戸隠三十三窟の岩窟の中にあり、第一本窟が奥社本殿だったと言われています。

「奥社」は、日本神話にある「天照大神」が天の岩屋にお隠れになった時、無双の神力をもって、天の岩戸をお開きになった「天手力男命」を戸隠山の麓に奉斎した事に始まります。
戸隠神社の御本社として全国に開運、心願成就、五穀豊熟、スポーツ必勝などの御神徳が広宣され多くの崇敬者が登拝されます。

かつて奥社社務所に籠る役は、本院燈明役(とうみょうやく)と言われ、衆徒(寺の僧徒のこと)が2年交代で務め、事故がない限り下山できないほど重要なお勤めとされてきたらしい。
俗世間から切り離されたこの秘境での修行を思うと、言葉では伝えられない壮絶さが想像されます。
「奥社」から空を見上げると、切り立った岸壁の戸隠山が迫ってくるように感じます。

今日のように青空に“凛”と立つ戸隠山を背にした「奥社」は本当に見事で美しい。しかし、季節はまもなく「冬」。この切り立った岩璧から吹き降ろす雪と風に耐えなくてはなりません。
そんな自然の摂理を思うと、あの詩を思い出します。
「戸かくし姫」
山は鋸(のこぎり)の歯の形
冬になれば 人は往かず
峰の風に 屋根と木が鳴る
こうこうと鳴ると云ふ
「そんなに こうこうつて鳴りますか」
私の問ひに
娘は皓(しろ)い歯を見せた
遠くの薄は夢のやう
「美しい時ばかりはございません」
初冬の山は 不開(あけず)の間
峰吹く風をききながら
不開の間では
坊の娘がお茶をたててゐる
二十(はたち)を越すと早いものと
娘は年齢(とし)を云はなかつた
山は鋸(のこぎり)の歯の形
冬になれば 人は往かず
峰の風に 屋根と木が鳴る
こうこうと鳴ると云ふ
「そんなに こうこうつて鳴りますか」
私の問ひに
娘は皓(しろ)い歯を見せた
遠くの薄は夢のやう
「美しい時ばかりはございません」
初冬の山は 不開(あけず)の間
峰吹く風をききながら
不開の間では
坊の娘がお茶をたててゐる
二十(はたち)を越すと早いものと
娘は年齢(とし)を云はなかつた
津村信夫
ここで、「戸隠古道」の旅は終わりとなります。
「一の鳥居」から「奥社」までは、やはり長い道のりでした。「修行」などと大それたものではありませんが、石柱が立つ戸隠由縁の地を一つ一つ丁寧に周りながら、その場所に伝わる話に耳を傾けていると、自然と古の人たちの声が聞こえてくるようでした。
そして、その声に今の自分を重ねながら歩いた「戸隠古道」はとても楽しい時間となりました。
ぜひ、みなさんも四季折々にいろんな表情を見せてくれる自然豊かなこの道を、ゆっくりと時間をかけて歩かれたらいかがでしょうか。
さて、読者の皆様には大変お世話になりましたが、この記事をもって、私、堀内は筆を置かせていただくこととなりました。
約一年という短い間でしたが、充実した時を過ごさせていただきました。
今後は後任の高橋が、皆様にいいときエリアの旬な情報をお届けいたしますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
本当にありがとうございました。
2012年11月20日
戸隠古道を行く!!その29 「九頭龍社」

石段をゆっくり上りきると、目の前には「九頭龍社」が鎮座しています。

九頭竜社の創建は定かではないようですが。戸隠神社が勧請される遥か以前から信仰された地元神とされているようです。
 案内板によると「地主の神で御鎮座年代古く天岩戸戸隠山の守神にして神代の岩戸隠れの変に御功績を立てました御祭神天手力男命を当山にお迎えした大神で水分神、水口神、五穀の神、開運守護魔除の神、虫歯の神として御霊験あらたかに国民の多幸弥栄の上に高大なる御神徳を恵み給う大神様です。」とあります。
案内板によると「地主の神で御鎮座年代古く天岩戸戸隠山の守神にして神代の岩戸隠れの変に御功績を立てました御祭神天手力男命を当山にお迎えした大神で水分神、水口神、五穀の神、開運守護魔除の神、虫歯の神として御霊験あらたかに国民の多幸弥栄の上に高大なる御神徳を恵み給う大神様です。」とあります。
縁起によると、嘉祥2年(849年)、飯縄山に籠もった学問行者によって開山されたとされ、祭神はこの地の沼に住んでいた龍神「九頭龍大神(くずりゅうのおおかみ)」で、学問行者入山以前から戸隠の地主神として信仰されてきたと言われています。 龍神は、命の源の水を司る水の神様で、その恵みに感謝し、五穀豊穣や心願成就の神様とされているそうです。現在も毎日、神饌所(しんせんじょ)で炊いたご飯を本殿にお供えする儀式が行われ、戸隠信仰の古態が今も続けられていることに改めて驚き、脈々と続く信仰の深さを感じました。
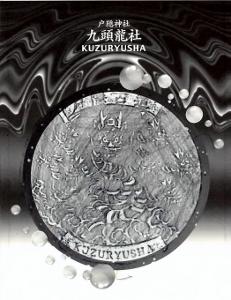
いよいよ最終地点「奥社」へと向かいます。
2012年11月19日
戸隠古道を行く!!その28 「奥社参道杉並木」
「奥社参道口」から約1kmほど歩くと「随神門」が見えてきます。

「随神門(ずいじんもん)」とは「随身」とも書くらしく、神域に邪悪なものが入り来るのを防ぐ御門の神をまつる門のことらしい。
ここ戸隠の随神門は神仏習合の時代には仁王門だったそうです。
この「随神門」を守るように鎮座している狛犬の脇に石柱が立っています。

今回は拓本を取ってから先に進むとします。

ちょうどこの拓本は「随神門」から見た杉並木を描いたものです。
実際はこんな感じ・・・

ここを抜けると、樹齢400年以上の杉並木が続く参道になります。

何回来ても、やっぱりこの見事な杉並木を時々立ち止まっては見上げます。
400歳を超える杉の迫力に圧倒されて自分が小さく感じて・・・
天に伸びる木の先を目で追うと、身体が後ろに倒れてしまいそうです。
前を向けば遙かに続く杉並木。
振り返れば、杉並木の向こうに先ほどの「随神門」。
この先には、平安期から明治まで続いた本院十二坊のなごりの石積などが残っています。
更に石段を上がると・・・

杉並木が終わった参道の右側奥にはぽっかり空いた草原空間があります。承徳2年に建てられたと言われる「講堂跡」。
残された礎石から間口13間半(約25m)、奥行7間半(約13.5m)と広大な建物に、多くの修験者が集い隆盛を極めていたと伝えられています。
ここを過ぎればもうすぐ「九頭龍社」。石段をゆっくり上がります。

「随神門(ずいじんもん)」とは「随身」とも書くらしく、神域に邪悪なものが入り来るのを防ぐ御門の神をまつる門のことらしい。
ここ戸隠の随神門は神仏習合の時代には仁王門だったそうです。
この「随神門」を守るように鎮座している狛犬の脇に石柱が立っています。

今回は拓本を取ってから先に進むとします。

ちょうどこの拓本は「随神門」から見た杉並木を描いたものです。
実際はこんな感じ・・・

ここを抜けると、樹齢400年以上の杉並木が続く参道になります。

何回来ても、やっぱりこの見事な杉並木を時々立ち止まっては見上げます。
400歳を超える杉の迫力に圧倒されて自分が小さく感じて・・・
天に伸びる木の先を目で追うと、身体が後ろに倒れてしまいそうです。
前を向けば遙かに続く杉並木。
振り返れば、杉並木の向こうに先ほどの「随神門」。
この先には、平安期から明治まで続いた本院十二坊のなごりの石積などが残っています。
更に石段を上がると・・・

杉並木が終わった参道の右側奥にはぽっかり空いた草原空間があります。承徳2年に建てられたと言われる「講堂跡」。
残された礎石から間口13間半(約25m)、奥行7間半(約13.5m)と広大な建物に、多くの修験者が集い隆盛を極めていたと伝えられています。
ここを過ぎればもうすぐ「九頭龍社」。石段をゆっくり上がります。
2012年11月16日
半ざる食べ歩きin戸隠 その2
その1からの続き→
4件目は「しなの屋」さんへ



おそばは風味豊か(o^_^o)
新そばの時期は自家栽培のそばをつかっているんですって
そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。平らな形をしたそば団子は素朴な味わいでした。
最後、5件目は「大久保西の茶屋」さんへ


古民家を思わせる佇まい。店内も昭和レトロ感たっぷり
自家農園で収穫された新そばが沢山積み上げられていました。


やわらかくのど越しのよい麺。
そば猪口を持参した特典は、ここでは何と!そばソフトクリーム。
甘さ控えめのさっぱりしたお味。
写真のUPでおわかりかと思いますが、〝ご利益そば猪口〟の特典もあり、おそばの他にもかなりいただいております!
一気に5件をまわったのですが、かなり満腹になりました(笑)
〝そば猪口〟をお持ちでない方でも、5件分のおそばは十分満足いただけるはず。
今回、食べ歩いて感じたのは、どこのお店にもそれぞれの味があり、それぞれの個性があってとても美味しかったこと。
ほかのお店も行きたかったなー
皆さんも、ゆっくり時間をかけて戸隠散策をしながらお気に入りのそば屋さんを見つけに行ってみませんか?(^∀^ )

5軒のスタンプを集めて応募すると抽選で年越そばがあたります。
私も早く応募しなきゃ
※戸隠は雪が降りましたので、これからお越しの際には気を付けてお越し下さい
開催期間は11月25日(日)まで。
残り期間も少ないですから、ぜひ今から計画して戸隠の新そばをお楽しみください。
詳しくはこちら→戸隠そば祭り
4件目は「しなの屋」さんへ



おそばは風味豊か(o^_^o)
新そばの時期は自家栽培のそばをつかっているんですって

そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。平らな形をしたそば団子は素朴な味わいでした。
最後、5件目は「大久保西の茶屋」さんへ


古民家を思わせる佇まい。店内も昭和レトロ感たっぷり

自家農園で収穫された新そばが沢山積み上げられていました。


やわらかくのど越しのよい麺。
そば猪口を持参した特典は、ここでは何と!そばソフトクリーム。
甘さ控えめのさっぱりしたお味。
写真のUPでおわかりかと思いますが、〝ご利益そば猪口〟の特典もあり、おそばの他にもかなりいただいております!
一気に5件をまわったのですが、かなり満腹になりました(笑)
〝そば猪口〟をお持ちでない方でも、5件分のおそばは十分満足いただけるはず。
今回、食べ歩いて感じたのは、どこのお店にもそれぞれの味があり、それぞれの個性があってとても美味しかったこと。

ほかのお店も行きたかったなー
皆さんも、ゆっくり時間をかけて戸隠散策をしながらお気に入りのそば屋さんを見つけに行ってみませんか?(^∀^ )

5軒のスタンプを集めて応募すると抽選で年越そばがあたります。
私も早く応募しなきゃ

※戸隠は雪が降りましたので、これからお越しの際には気を付けてお越し下さい

開催期間は11月25日(日)まで。
残り期間も少ないですから、ぜひ今から計画して戸隠の新そばをお楽しみください。
詳しくはこちら→戸隠そば祭り
2012年11月16日
半ざる食べ歩きin戸隠 その1
只今、戸隠にて「半ざる食べ歩き」が開催中!
今が旬の新そば さっそく行ってまりました
さっそく行ってまりました
まずは長野市商工会戸隠支所に伺い〝半ざる食べ歩き手形〟をゲット
手形は、実施そば店でも購入可能。
 手形には半ざる券が5枚ついています。
手形には半ざる券が5枚ついています。
その他に、〝スタンプ台紙〟と〝戸隠そば達人への手引きⅣ〟という冊子もいただけます。
さて、ここで更にお得な情報!
〝ご利益そば猪口(9月30日に行われた「大盤振る舞いそば」に行かれた人には更に特典があり、その時に購入した物です。)〟を持っていくと各店でサービスが受けられます

実施そば屋約20店の中から、まずは・・・
1件目は「そばの実」さんへ

 お店はお客様でいっぱい、店内の待合室も手形をもったお客様であふれていました!
お店はお客様でいっぱい、店内の待合室も手形をもったお客様であふれていました!
待つ事しばし・・席に案内され手形で半ざるを注文。
おそばは、待った甲斐あり コシがあっておいしかったです。
コシがあっておいしかったです。
そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。まわりはかりっと中はもっちり(^ω^o)
2件目は「山口屋」さんへ

入り口の水車が目をひきます。隣りにはお土産屋さんも併設させていますよ♪

 麺はやわらかめで、そばつゆはお出汁の味がきいています。
麺はやわらかめで、そばつゆはお出汁の味がきいています。
そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。しっかりと歯ごたえのあるお団子です。
3件目は「仁王門屋」さんへ


 つるっとのど越しのよい麺でした。
つるっとのど越しのよい麺でした。
小鉢のお野菜にかかっているのがゴマとクルミの特製ダレ。コクがあっておいしかったです。
そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。
ボリュームいっぱいでみたらし餡、特製ダレの2種類の味が楽しめます
今が旬の新そば
 さっそく行ってまりました
さっそく行ってまりました
まずは長野市商工会戸隠支所に伺い〝半ざる食べ歩き手形〟をゲット

手形は、実施そば店でも購入可能。

その他に、〝スタンプ台紙〟と〝戸隠そば達人への手引きⅣ〟という冊子もいただけます。
さて、ここで更にお得な情報!
〝ご利益そば猪口(9月30日に行われた「大盤振る舞いそば」に行かれた人には更に特典があり、その時に購入した物です。)〟を持っていくと各店でサービスが受けられます

実施そば屋約20店の中から、まずは・・・
1件目は「そばの実」さんへ


 お店はお客様でいっぱい、店内の待合室も手形をもったお客様であふれていました!
お店はお客様でいっぱい、店内の待合室も手形をもったお客様であふれていました!待つ事しばし・・席に案内され手形で半ざるを注文。
おそばは、待った甲斐あり
 コシがあっておいしかったです。
コシがあっておいしかったです。そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。まわりはかりっと中はもっちり(^ω^o)
2件目は「山口屋」さんへ

入り口の水車が目をひきます。隣りにはお土産屋さんも併設させていますよ♪

 麺はやわらかめで、そばつゆはお出汁の味がきいています。
麺はやわらかめで、そばつゆはお出汁の味がきいています。そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。しっかりと歯ごたえのあるお団子です。
3件目は「仁王門屋」さんへ


 つるっとのど越しのよい麺でした。
つるっとのど越しのよい麺でした。小鉢のお野菜にかかっているのがゴマとクルミの特製ダレ。コクがあっておいしかったです。
そば猪口を持参した特典はそば団子のサービス。
ボリュームいっぱいでみたらし餡、特製ダレの2種類の味が楽しめます

2012年11月15日
戸隠古道を行く!!その27 「奥社参道口」
いよいよゴールが近づいてきました。
今日ご紹介する「奥社参道口」は、戸隠古道の最終目的地「奥社」への入り口です。

この鳥居の前にあるお茶屋は明治創業の「なおすけ」。

「なおすけ」については、過去記事「奥社前 なおすけ」をご覧ください。
その脇にはきれいな清水が流れています。この小川は「鳥居川」と言いますが、小川の流れが戸隠方向ではなくて山側の信濃町方向に流れていくため、別名「逆川(さかさがわ)」とも呼ばれています。

この小川にかかる橋を渡ると、“大鳥居”がどっしりと構えており、そこから広い参道がまっすぐ伸びています。
その“大鳥居”の手前には「下馬碑」があります。
 「下馬」とは、これより先の乗馬を禁ずるということで、「下馬碑」はその場所を示しています。
「下馬」とは、これより先の乗馬を禁ずるということで、「下馬碑」はその場所を示しています。
本によると、江戸城では、下馬所で大名や役高500石以上の役人、高家、交代寄合等の「乗輿以上」の格を有した者以外は、馬や駕籠から降りなければならず、乗輿以上の格であっても、下馬所より先は供連の人数を制限されたと記されているようです。
それだけ格式高い場所ということがわかります。
戸隠山を仰ぎながら“大鳥居”の前に立つと、何だか「これから参道へ入ります。よろしくお願いします。」という気持ちになって自然と一礼をしてしまう。
そんな威厳と風格のある“大鳥居”をいよいよくぐり、「随神門」より広がる「奥社参道杉並木」へと向かいます。

今日ご紹介する「奥社参道口」は、戸隠古道の最終目的地「奥社」への入り口です。

この鳥居の前にあるお茶屋は明治創業の「なおすけ」。

「なおすけ」については、過去記事「奥社前 なおすけ」をご覧ください。
その脇にはきれいな清水が流れています。この小川は「鳥居川」と言いますが、小川の流れが戸隠方向ではなくて山側の信濃町方向に流れていくため、別名「逆川(さかさがわ)」とも呼ばれています。

この小川にかかる橋を渡ると、“大鳥居”がどっしりと構えており、そこから広い参道がまっすぐ伸びています。
その“大鳥居”の手前には「下馬碑」があります。
 「下馬」とは、これより先の乗馬を禁ずるということで、「下馬碑」はその場所を示しています。
「下馬」とは、これより先の乗馬を禁ずるということで、「下馬碑」はその場所を示しています。本によると、江戸城では、下馬所で大名や役高500石以上の役人、高家、交代寄合等の「乗輿以上」の格を有した者以外は、馬や駕籠から降りなければならず、乗輿以上の格であっても、下馬所より先は供連の人数を制限されたと記されているようです。
それだけ格式高い場所ということがわかります。
戸隠山を仰ぎながら“大鳥居”の前に立つと、何だか「これから参道へ入ります。よろしくお願いします。」という気持ちになって自然と一礼をしてしまう。
そんな威厳と風格のある“大鳥居”をいよいよくぐり、「随神門」より広がる「奥社参道杉並木」へと向かいます。

2012年11月14日
戸隠古道を行く!!その26 「戸隠牧場」
「念仏池」から続く古道を歩くと、県道36号線に抜けます。この通りを渡ると、豊かな自然林に囲まれた「戸隠キャンプ場」が広がっています。

その脇を道なりに進み、「戸隠牧場」へ。

牧場の入口からは、四季折々の表情を見せる「戸隠山」が遠くに望めます。その見事な景色に見とれて、うっかり奥へ進んでしまいましたが・・・拓本を取るための石柱は、入口手前に。

まずは拓本を取ってから、「戸隠牧場」へと向かいました。

このように美しくのどかな「戸隠牧場」の成り立ちは明治42年。
その後、第二次世界大戦が始まり、食糧不足から牧場は畑に転用され一時的に閉鎖となります。しかし、終戦後の昭和24年に再開されたということです。

そんな「戸隠牧場」も今では戸隠連峰、飯縄山、黒姫山に囲まれた素晴らしいビューポイントとして知られており、多くのカメラマンが四季折々の表情を撮りに訪れます。

6月~10月中旬のオンシーズンには、たくさんの牛や馬が放牧され、間近で見ることができます。
この日も柔らかな日差しの中、のんびりと草を食んだり、ウトウトする牛の
のどかな風景が見られました。
牧場内にある「自然観察動物園」では、うさぎやアヒル、ヤギなどと触れ合えたり、乗馬体験も出来ます。
「戸隠古道」を歩き始めて26カ所目の「戸隠牧場」はそれまでの戸隠由縁の地とは少し違う感覚を覚えました。解放的で美しい自然の中に動物がいるという風景がそうさせるのか・・・。
それまでの神秘的な空気感とは違う穏やかでほっこりした気持ちになれました。
※取材したのは10月中旬だったため、現在は放牧されておりません。
去りがたい思いを抑えて、次の「奥社参道口」へ足を進めます。

その脇を道なりに進み、「戸隠牧場」へ。

牧場の入口からは、四季折々の表情を見せる「戸隠山」が遠くに望めます。その見事な景色に見とれて、うっかり奥へ進んでしまいましたが・・・拓本を取るための石柱は、入口手前に。

まずは拓本を取ってから、「戸隠牧場」へと向かいました。

このように美しくのどかな「戸隠牧場」の成り立ちは明治42年。
その後、第二次世界大戦が始まり、食糧不足から牧場は畑に転用され一時的に閉鎖となります。しかし、終戦後の昭和24年に再開されたということです。

そんな「戸隠牧場」も今では戸隠連峰、飯縄山、黒姫山に囲まれた素晴らしいビューポイントとして知られており、多くのカメラマンが四季折々の表情を撮りに訪れます。

6月~10月中旬のオンシーズンには、たくさんの牛や馬が放牧され、間近で見ることができます。
この日も柔らかな日差しの中、のんびりと草を食んだり、ウトウトする牛の
のどかな風景が見られました。
牧場内にある「自然観察動物園」では、うさぎやアヒル、ヤギなどと触れ合えたり、乗馬体験も出来ます。
「戸隠古道」を歩き始めて26カ所目の「戸隠牧場」はそれまでの戸隠由縁の地とは少し違う感覚を覚えました。解放的で美しい自然の中に動物がいるという風景がそうさせるのか・・・。
それまでの神秘的な空気感とは違う穏やかでほっこりした気持ちになれました。
※取材したのは10月中旬だったため、現在は放牧されておりません。
去りがたい思いを抑えて、次の「奥社参道口」へ足を進めます。
2012年11月13日
戸隠古道を行く!!その25 「念仏池」
前回の「女人結界の碑」から熊笹が茂る古道を通って来ると、「念仏池」に辿り着きます。

車で来る場合は、県道36号線を戸隠キャンプ場に向かって進むと、

右手に見えてくる「念仏池」の石碑が目印です。

この池には昔話が伝わります。
親鸞上人が戸隠参詣の折、中道坊と言う寺に宿を乞い、親切なもてなしを受けて100日間逗留した時のお話。
 高妻山に登られた帰りのこと、小さな池を発見しました。不思議なことに池の底の砂がむくむくと動き、水泡が噴煙のように吹き出ていたので、親鸞聖人が「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と念仏を唱えると、これに応えるように池底の砂が勢いよく噴き上がり、声を低くすれば勢いが弱まりました。親鸞はこの*奇瑞(きずい)を喜んで、池の名を「念仏池」と名付けたそうです。
高妻山に登られた帰りのこと、小さな池を発見しました。不思議なことに池の底の砂がむくむくと動き、水泡が噴煙のように吹き出ていたので、親鸞聖人が「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と念仏を唱えると、これに応えるように池底の砂が勢いよく噴き上がり、声を低くすれば勢いが弱まりました。親鸞はこの*奇瑞(きずい)を喜んで、池の名を「念仏池」と名付けたそうです。
古道の途中に“ふっと”姿を現した「念仏池」。
木々に囲まれた池はとても澄んでいて、じっと見つめると異空間にいるような感じがしました。
「念仏池」の底からは、現在も水泡が噴出していました。
池の傍にある石柱には、このお話にちなんで親鸞聖人と沸々と湧く「念仏池」が描かれていました。


ここから続く古道を行くと、戸隠キャンプ場入口に出ます。次の「戸隠牧場」まではあと少し。
深まる秋を楽しみながら進みます。
*奇瑞とは、吉兆のこと。

車で来る場合は、県道36号線を戸隠キャンプ場に向かって進むと、

右手に見えてくる「念仏池」の石碑が目印です。

この池には昔話が伝わります。
親鸞上人が戸隠参詣の折、中道坊と言う寺に宿を乞い、親切なもてなしを受けて100日間逗留した時のお話。
 高妻山に登られた帰りのこと、小さな池を発見しました。不思議なことに池の底の砂がむくむくと動き、水泡が噴煙のように吹き出ていたので、親鸞聖人が「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と念仏を唱えると、これに応えるように池底の砂が勢いよく噴き上がり、声を低くすれば勢いが弱まりました。親鸞はこの*奇瑞(きずい)を喜んで、池の名を「念仏池」と名付けたそうです。
高妻山に登られた帰りのこと、小さな池を発見しました。不思議なことに池の底の砂がむくむくと動き、水泡が噴煙のように吹き出ていたので、親鸞聖人が「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と念仏を唱えると、これに応えるように池底の砂が勢いよく噴き上がり、声を低くすれば勢いが弱まりました。親鸞はこの*奇瑞(きずい)を喜んで、池の名を「念仏池」と名付けたそうです。古道の途中に“ふっと”姿を現した「念仏池」。
木々に囲まれた池はとても澄んでいて、じっと見つめると異空間にいるような感じがしました。
「念仏池」の底からは、現在も水泡が噴出していました。
池の傍にある石柱には、このお話にちなんで親鸞聖人と沸々と湧く「念仏池」が描かれていました。


ここから続く古道を行くと、戸隠キャンプ場入口に出ます。次の「戸隠牧場」まではあと少し。
深まる秋を楽しみながら進みます。
*奇瑞とは、吉兆のこと。
2012年11月12日
「ココット」に行ってきました!!
今日のランチは、「レストラン ココット」さんに行っていましたヽ(^▽^)ノ
昭和53年に開業されて、当時は市内の柳町にありましたが現在の飯綱高原に移って21年、ご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
お店は緑に囲まれた所にあります

店内に入ると、まず目にとまったのが暖炉(=^ ^=)
暖かみのある店内です
今日いただいたのは・・↓↓


サービスランチ(ライスorパン+ドリンク付)の中から、ミソアジハンバーグをチョイス♪
ミソアジハンバーグはその名の通り、味噌味のソースがかかっているハンバーグ!!
珍しいですよね?
オーナーのオリジナルミソソースは甘くてまろやかでしょっぱすぎないお味♪
ハンバーグはというと本当に柔らかくてふわふわの食感(o^_^o)♪
柔らかさの秘密は、オーナーこだわりの部位である〝牛のうちもも〟のすじを丁寧にとり、赤身となったところに〝ケンネ脂(※)〟を入れて作っているそうです。手間がかかっているんですね~

この他にもオーナーの手作りにこだわったお料理が沢山
 こちらのヨーグルト、上にのっている〝りんご〟のジャムも手作り
こちらのヨーグルト、上にのっている〝りんご〟のジャムも手作り
ジャムは季節によって〝いちご〟が登場する事もあるそうです♪
オーナー曰く〝加工8割営業2割〟の手間暇かけたこだわりのお料理、ぜひ堪能してみてはいかがでしょうか?
(※)ケンネ脂とは牛の腎臓のまわりの油で、入れる事によってさらにお肉が柔らかくなるそうです。
レストランココットはこちら☟
場所:〒380-0888 長野市上ヶ屋2471-1867
電話 : 026-239-3096
HP : http://www5e.biglobe.ne.jp/~cocotte/frame.html
昭和53年に開業されて、当時は市内の柳町にありましたが現在の飯綱高原に移って21年、ご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
お店は緑に囲まれた所にあります


店内に入ると、まず目にとまったのが暖炉(=^ ^=)

暖かみのある店内です

今日いただいたのは・・↓↓


サービスランチ(ライスorパン+ドリンク付)の中から、ミソアジハンバーグをチョイス♪
ミソアジハンバーグはその名の通り、味噌味のソースがかかっているハンバーグ!!
珍しいですよね?
オーナーのオリジナルミソソースは甘くてまろやかでしょっぱすぎないお味♪
ハンバーグはというと本当に柔らかくてふわふわの食感(o^_^o)♪
柔らかさの秘密は、オーナーこだわりの部位である〝牛のうちもも〟のすじを丁寧にとり、赤身となったところに〝ケンネ脂(※)〟を入れて作っているそうです。手間がかかっているんですね~


この他にもオーナーの手作りにこだわったお料理が沢山

 こちらのヨーグルト、上にのっている〝りんご〟のジャムも手作り
こちらのヨーグルト、上にのっている〝りんご〟のジャムも手作り
ジャムは季節によって〝いちご〟が登場する事もあるそうです♪
オーナー曰く〝加工8割営業2割〟の手間暇かけたこだわりのお料理、ぜひ堪能してみてはいかがでしょうか?
(※)ケンネ脂とは牛の腎臓のまわりの油で、入れる事によってさらにお肉が柔らかくなるそうです。
レストランココットはこちら☟
場所:〒380-0888 長野市上ヶ屋2471-1867
電話 : 026-239-3096
HP : http://www5e.biglobe.ne.jp/~cocotte/frame.html
2012年11月09日
戸隠古道を行く!!その24 「女人結界の碑」
秋も深まった越後道を進みます。
越後から戸隠への最短脇道ルートの越後道は、信濃町古間を起点に戸隠に向かう道です。

紅葉も散りはじめ、散策道に落ちた葉を踏むと軽やかな音が耳に楽しい。
越後道越水ヶ原の分岐点に立つ石碑が「女人結界の碑」です。


拓本帳によると、この碑は、高さ190センチの自然石で、寛政7年に近江彦根 山中為之進が建立したとのことです。
石面には、「右奥院・中院両道女人結界、左中院江之女人道」という文字が刻まれています。
女人結界とは、「女人禁制の地域」のことで聖地・霊域とされる所に女人の進入を禁じることです。仏教の戒律としても行われたり、修験道が全盛だったころには修行の妨げになるとして、女性を神域に立ち入らせない女人禁制の定めがありました。(今では信じられませんが )
)
そこで、「男道」「女道」を区別することで、女性参拝者が奥院道・中院道へ立ち入るのを禁じ、奥院に向かわせないように建てた碑です。
昔は、このような地がほかにも多く合ったようで、拓本帳には次のようなことが書かれています。
江戸時代後期の旅行家であり民俗学者でもある「菅江真澄(すがえますみ)」は、全国を遊歴する中で信州にも入り「久米路の橋」(長野市信州新町)「伊那の中路」などの記行文を残したと言われています。
「久米路の橋」での一節。
・・・このみまえを、左にのぼれば、二丘尼石、観音ぼさつの堂あり。麓より女、この堂を限りにまう出てぞ、みな帰りいにける。・・・

越後から戸隠への最短脇道ルートの越後道は、信濃町古間を起点に戸隠に向かう道です。

紅葉も散りはじめ、散策道に落ちた葉を踏むと軽やかな音が耳に楽しい。
越後道越水ヶ原の分岐点に立つ石碑が「女人結界の碑」です。


拓本帳によると、この碑は、高さ190センチの自然石で、寛政7年に近江彦根 山中為之進が建立したとのことです。
石面には、「右奥院・中院両道女人結界、左中院江之女人道」という文字が刻まれています。
女人結界とは、「女人禁制の地域」のことで聖地・霊域とされる所に女人の進入を禁じることです。仏教の戒律としても行われたり、修験道が全盛だったころには修行の妨げになるとして、女性を神域に立ち入らせない女人禁制の定めがありました。(今では信じられませんが
 )
)そこで、「男道」「女道」を区別することで、女性参拝者が奥院道・中院道へ立ち入るのを禁じ、奥院に向かわせないように建てた碑です。
昔は、このような地がほかにも多く合ったようで、拓本帳には次のようなことが書かれています。
江戸時代後期の旅行家であり民俗学者でもある「菅江真澄(すがえますみ)」は、全国を遊歴する中で信州にも入り「久米路の橋」(長野市信州新町)「伊那の中路」などの記行文を残したと言われています。
「久米路の橋」での一節。
・・・このみまえを、左にのぼれば、二丘尼石、観音ぼさつの堂あり。麓より女、この堂を限りにまう出てぞ、みな帰りいにける。・・・

2012年11月08日
戸隠古道を行く!!その23 「稚児の塔」
すこし肌寒くなった古道を行くと、その脇に苔むした三つ石塔がひっそりと佇んでいます。

この塔は、応永6年に建立されたと言われています。
両側には応永の年号が刻まれた宝篋印塔(ほうきょういんとう)、真ん中はかすかに「児」の字が読み取れる碑が「稚児の塔」です。
戸隠には「稚児の塔」の由来となる民話が伝わっています。
その民話とは・・・
 その昔、仲良く暮らす夫婦がいたそうです。夫 忠清は武術に長けていましたが、字が読めませんでした。そんな夫は家名を上げるため木曽義仲の家来になり戦に加わりましたが、敗れて家に戻ると妻は子の智悟を生んで亡くなっていました。その子を妻のいとこの葵が育てていてくれたことから、忠清はこの葵を妻にめとり暮らしましたが、葵がその子をかわいがらなかったことから、わが子を立派なお坊さんにしようと出家させたと言います。その後、忠清は再び隠密として頼朝の首を狙いますが、それも叶わず家に戻ると妻の態度がよそよそしいことに気づきます。
その昔、仲良く暮らす夫婦がいたそうです。夫 忠清は武術に長けていましたが、字が読めませんでした。そんな夫は家名を上げるため木曽義仲の家来になり戦に加わりましたが、敗れて家に戻ると妻は子の智悟を生んで亡くなっていました。その子を妻のいとこの葵が育てていてくれたことから、忠清はこの葵を妻にめとり暮らしましたが、葵がその子をかわいがらなかったことから、わが子を立派なお坊さんにしようと出家させたと言います。その後、忠清は再び隠密として頼朝の首を狙いますが、それも叶わず家に戻ると妻の態度がよそよそしいことに気づきます。
ある時、妻の留守中、男から届いた妻宛ての書状で妻の不義密通をうたがいますが、字が読めない父は戸隠山東光院で修業中のわが子を呼び寄せ書状を読ませました。信じがたい義母への艶文を手に、智悟は悩みますが「義母の難儀を救い、父の安穏を願うためらな、神仏もお咎めすまい」と、内容を時候の挨拶と偽り読み聞かせたといいます。夫は妻を疑った己を恥じ、妻は不倫の罪を後悔し、ともに剃髪。子は孝行のためとはいえ、父を欺き、仏の教えに背いたとして、東光院住職への道を捨て、一宇の庵を建てて生涯を送ったと言うお話です。

賢さと両親を思う優しさのあまり悲しい末路となった孝行息子のお話は、読んでいてとても切なく感じました。
その霊を供養して建てられた「稚児の塔」に手を合わせて次の「女人結界の碑」へ進みます。

この塔は、応永6年に建立されたと言われています。
両側には応永の年号が刻まれた宝篋印塔(ほうきょういんとう)、真ん中はかすかに「児」の字が読み取れる碑が「稚児の塔」です。
戸隠には「稚児の塔」の由来となる民話が伝わっています。
その民話とは・・・
 その昔、仲良く暮らす夫婦がいたそうです。夫 忠清は武術に長けていましたが、字が読めませんでした。そんな夫は家名を上げるため木曽義仲の家来になり戦に加わりましたが、敗れて家に戻ると妻は子の智悟を生んで亡くなっていました。その子を妻のいとこの葵が育てていてくれたことから、忠清はこの葵を妻にめとり暮らしましたが、葵がその子をかわいがらなかったことから、わが子を立派なお坊さんにしようと出家させたと言います。その後、忠清は再び隠密として頼朝の首を狙いますが、それも叶わず家に戻ると妻の態度がよそよそしいことに気づきます。
その昔、仲良く暮らす夫婦がいたそうです。夫 忠清は武術に長けていましたが、字が読めませんでした。そんな夫は家名を上げるため木曽義仲の家来になり戦に加わりましたが、敗れて家に戻ると妻は子の智悟を生んで亡くなっていました。その子を妻のいとこの葵が育てていてくれたことから、忠清はこの葵を妻にめとり暮らしましたが、葵がその子をかわいがらなかったことから、わが子を立派なお坊さんにしようと出家させたと言います。その後、忠清は再び隠密として頼朝の首を狙いますが、それも叶わず家に戻ると妻の態度がよそよそしいことに気づきます。ある時、妻の留守中、男から届いた妻宛ての書状で妻の不義密通をうたがいますが、字が読めない父は戸隠山東光院で修業中のわが子を呼び寄せ書状を読ませました。信じがたい義母への艶文を手に、智悟は悩みますが「義母の難儀を救い、父の安穏を願うためらな、神仏もお咎めすまい」と、内容を時候の挨拶と偽り読み聞かせたといいます。夫は妻を疑った己を恥じ、妻は不倫の罪を後悔し、ともに剃髪。子は孝行のためとはいえ、父を欺き、仏の教えに背いたとして、東光院住職への道を捨て、一宇の庵を建てて生涯を送ったと言うお話です。
「戸隠の民話」より

賢さと両親を思う優しさのあまり悲しい末路となった孝行息子のお話は、読んでいてとても切なく感じました。
その霊を供養して建てられた「稚児の塔」に手を合わせて次の「女人結界の碑」へ進みます。
2012年11月07日
Cafe&Gallery いろはな
「いいときいろどり」をご覧の皆様、はじめまして
新たにいいとき観光推進協議会の一員となりました、高橋と申します_(..)_
いいときの最新情報などをお伝えしていきますのでよろしくお願いします。
今回ご紹介するのは、「Cafe&Gallery いろはな」
「いろはな」さんは、鬼無里にあるおやきのいろは堂さんに併設されています。
1Fはカフェになっており、おやきをはじめとして、スイーツも味わうことができます
カフェに関しては以前のブログ:いよいよopen! cafe & gallery「いろはな」をご覧ください
今回は2Fにあるギャラリーをご紹介します。
カフェを抜けて階段を上がると、静かな時間の流れる空間が広がっていました

無料のギャラリーとなっており、約3週間ほどで展示物がかわり、今は伊藤忠雄さんの作品が展示されています(^_^)

ガラスにアクリル絵の具を使用して絵を描いているとのこと!!〝ガラスに描く〟という発想・・思いつかないですよね(・〇・;)!!芸術家の方の発想力ってすごい
作品の中には、チべットやエジプトをイメージして描かれているものもあり、透明なガラスに鮮やかに描かれた神秘的な世界が広がっていました・:。+゜・*。:・
また、その隣りのブースには原山恵さんのワイヤービーズアクセサリー展が開催されています。
耳にかけて使う珍しいピアスや、ペンダントトップ、手作りのかわいいアクセサリーが沢山
購入も可能です


カフェでティータイムを楽しみながら、芸術の秋を堪能させて頂きました♫
開催期間
伊藤忠雄 ガラス絵展 平成24年10月24日~平成24年11月12日
原山恵 ワイヤービーズアクセサリー展 平成24年10月1日~平成24年12月30日
お早目にどうぞ
詳しくは→いろは堂カフェ&ギャラリー

新たにいいとき観光推進協議会の一員となりました、高橋と申します_(..)_

いいときの最新情報などをお伝えしていきますのでよろしくお願いします。
今回ご紹介するのは、「Cafe&Gallery いろはな」

「いろはな」さんは、鬼無里にあるおやきのいろは堂さんに併設されています。
1Fはカフェになっており、おやきをはじめとして、スイーツも味わうことができます

カフェに関しては以前のブログ:いよいよopen! cafe & gallery「いろはな」をご覧ください

今回は2Fにあるギャラリーをご紹介します。
カフェを抜けて階段を上がると、静かな時間の流れる空間が広がっていました


無料のギャラリーとなっており、約3週間ほどで展示物がかわり、今は伊藤忠雄さんの作品が展示されています(^_^)

ガラスにアクリル絵の具を使用して絵を描いているとのこと!!〝ガラスに描く〟という発想・・思いつかないですよね(・〇・;)!!芸術家の方の発想力ってすごい

作品の中には、チべットやエジプトをイメージして描かれているものもあり、透明なガラスに鮮やかに描かれた神秘的な世界が広がっていました・:。+゜・*。:・
また、その隣りのブースには原山恵さんのワイヤービーズアクセサリー展が開催されています。
耳にかけて使う珍しいピアスや、ペンダントトップ、手作りのかわいいアクセサリーが沢山

購入も可能です



カフェでティータイムを楽しみながら、芸術の秋を堪能させて頂きました♫
開催期間
伊藤忠雄 ガラス絵展 平成24年10月24日~平成24年11月12日
原山恵 ワイヤービーズアクセサリー展 平成24年10月1日~平成24年12月30日
お早目にどうぞ

詳しくは→いろは堂カフェ&ギャラリー
2012年11月06日
戸隠トレイルランレース応援ありがとうございました!!
11月4日に戸隠トレイルランレースが開催されました。
朝からとてもいい天気に恵まれました

戸隠山もくっきり!気温は-5℃・・・
名誉大会長である鷲沢長野市長の合図でスタート!
3種類のコース設定があり、
ロングコース(45km)はAM7:00スタート参加者:約350人
ミドルコース(28km)はAM9:00スタート参加者:約350人
ジュニア&ビギナーコース、チームチャレンジコース(6km)参加者:約200人
トータルで約900人もの参加者で開催されました。
途中のエイドステーションでは、ボランティアの方たちが選手をサポート

またゴール地点ではアウトドアフェスタが開催されていました♫
最後まで完走された皆さんおめでとうございました !!
!!
そして、応援に駆け付けて下さった皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m
レース結果はこちらから→http://www.togakushi-trail.jp/results/
朝からとてもいい天気に恵まれました


戸隠山もくっきり!気温は-5℃・・・

名誉大会長である鷲沢長野市長の合図でスタート!

3種類のコース設定があり、
ロングコース(45km)はAM7:00スタート参加者:約350人
ミドルコース(28km)はAM9:00スタート参加者:約350人
ジュニア&ビギナーコース、チームチャレンジコース(6km)参加者:約200人
トータルで約900人もの参加者で開催されました。
途中のエイドステーションでは、ボランティアの方たちが選手をサポート


またゴール地点ではアウトドアフェスタが開催されていました♫

最後まで完走された皆さんおめでとうございました
 !!
!!そして、応援に駆け付けて下さった皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m

レース結果はこちらから→http://www.togakushi-trail.jp/results/
2012年11月05日
戸隠古道を行く!!その22 「釈長明火定所」
「越水ヶ原」にある分岐点を“奥社道”へ進む。

少し歩くと右手の小高い場所に「釈長明火定所(しゃくちょうめいひさだめしょ)」の石柱がある。

ここは捨身供養を遂げた行者・釈長明を祀る場所。
この話は、永保年間のことと伝えられています。
長明は25歳で無言の行に入り、法華経を誦し3年間横になって寝ることなしという荒行を積むなど傑出した修行者であった。
「われ一切喜見菩薩なり、身を焚き、兜率天に上らんとす」と薪の上に坐し、火中で大往生を遂げたという。
この石柱の後方には、「宝篋印塔((ほうきょういんとう))」をぐるりと祠が取り囲んでいる。宝篋印塔とは、墓塔・供養塔などに使われる仏塔の一種。

おごそかで、とても不思議な空間でした。


少し歩くと右手の小高い場所に「釈長明火定所(しゃくちょうめいひさだめしょ)」の石柱がある。

ここは捨身供養を遂げた行者・釈長明を祀る場所。
この話は、永保年間のことと伝えられています。
長明は25歳で無言の行に入り、法華経を誦し3年間横になって寝ることなしという荒行を積むなど傑出した修行者であった。
「われ一切喜見菩薩なり、身を焚き、兜率天に上らんとす」と薪の上に坐し、火中で大往生を遂げたという。

この石柱の後方には、「宝篋印塔((ほうきょういんとう))」をぐるりと祠が取り囲んでいる。宝篋印塔とは、墓塔・供養塔などに使われる仏塔の一種。

おごそかで、とても不思議な空間でした。

2012年11月02日
戸隠トレランの応援に行こう!
11月3.4日に第4回信州戸隠トレイルランレース&アウトドアフェスタが開催されます。
約1,000人ものエントリーがあり、
ロングコース45Km、ミドルコース28Kmという山の中の長距離コースを走り回ります。
ロングコースはフルマラソンより長い!
初心者向けには6Kmのコースもあり、当日参加もできるそうです。
スタート地点の戸隠スキー場では、アウトドアフェスタも開催され、きのこ汁等の
ふるまいや協賛企業のブース出店もあるので、一般の方も楽しめますよ
ぜひ、選手の応援も兼ねて出かけてみてはいかがでしょう?
これまでの大会はこんな感じです。

詳しい情報はこちら→ http://www.togakushi-trail.jp/
約1,000人ものエントリーがあり、
ロングコース45Km、ミドルコース28Kmという山の中の長距離コースを走り回ります。
ロングコースはフルマラソンより長い!

初心者向けには6Kmのコースもあり、当日参加もできるそうです。
スタート地点の戸隠スキー場では、アウトドアフェスタも開催され、きのこ汁等の
ふるまいや協賛企業のブース出店もあるので、一般の方も楽しめますよ

ぜひ、選手の応援も兼ねて出かけてみてはいかがでしょう?
これまでの大会はこんな感じです。

詳しい情報はこちら→ http://www.togakushi-trail.jp/
2012年11月02日
戸隠古道を行く!!その21 「越水ヶ原」
いよいよ戸隠古道も残すところ10ヶ所。
21番目は「越水ヶ原」。

越水ヶ原は中社から奥社にかけて広がる自然豊かな場所で、この石柱からは「越水通り」や「高妻通り」、「つつじ通り」、「越後道」、「奥社道」などに道が分かれ、遊歩道がいくつも整備されていて、トレッキングをする多くの方たちに人気の場所です。
特にこの石柱から二股に分かれる「越水通り」と「越後道」には綺麗な花が見られます。
 ←クリックすると拡大されます。
←クリックすると拡大されます。
「越水通り(赤)」では、4月下旬から水芭蕉が咲き始め“美しい純白の苞”が楽しめるほか、夏にはヤナギラン、マツムシソウ、ワレモコウが見ごろとなります。また、「越後道(黄)」では、初夏のころからカタクリの花やレンゲツツジが訪問者の目を楽しませてくれます。


ここを訪れた紅葉の時期はこんな感じです。

越後街道沿いの紅葉
また空を見上げると、威風堂々と立つ戸隠連峰が間近に迫り、季節によって変わる表情を見ることもできます。その戸隠山を見ながら、多くの史跡と信仰が残る古道を進み、「釈長明火定所」へと向かいます。

21番目は「越水ヶ原」。

越水ヶ原は中社から奥社にかけて広がる自然豊かな場所で、この石柱からは「越水通り」や「高妻通り」、「つつじ通り」、「越後道」、「奥社道」などに道が分かれ、遊歩道がいくつも整備されていて、トレッキングをする多くの方たちに人気の場所です。
特にこの石柱から二股に分かれる「越水通り」と「越後道」には綺麗な花が見られます。
地図 / 戸隠観光協会
「越水通り(赤)」では、4月下旬から水芭蕉が咲き始め“美しい純白の苞”が楽しめるほか、夏にはヤナギラン、マツムシソウ、ワレモコウが見ごろとなります。また、「越後道(黄)」では、初夏のころからカタクリの花やレンゲツツジが訪問者の目を楽しませてくれます。


写真 / 戸隠観光協会パンフレット
ここを訪れた紅葉の時期はこんな感じです。

越後街道沿いの紅葉
また空を見上げると、威風堂々と立つ戸隠連峰が間近に迫り、季節によって変わる表情を見ることもできます。その戸隠山を見ながら、多くの史跡と信仰が残る古道を進み、「釈長明火定所」へと向かいます。

2012年11月01日
戸隠古道を行く!!その19 「硯石」
「小鳥ヶ池」から遊歩道をしばらく歩くとゆるやかな坂道になる。こ の道を登りきると眺めの良い小高い丘になっていた。

この場所にどっしりと構えたように鎮座する大石がある。これが、

「硯石」
 「硯石」にはこんなお話が。
「硯石」にはこんなお話が。
「鬼女紅葉(きじょもみじ)」の第一の家来「おまん」は剛力と健脚の女性で、荒倉山の合戦で紅葉と共に戦うが敗れてしまい敗走することになる。
そして平維茂(たいらのこれもち)らの追い手を振り切ってこの地まで逃げ切り、石にたまっていた雨水で血の付いた体を洗った。その時、この石に溜まった雨水が水鏡となり、そこに映った自分の姿があまりに恐ろしい鬼の形相だと知り、犯した罪の重さをを恥じる。
その後、中社勧修院で出家し、亡くなった方々を弔う日々の中、時にはこの場所で荒倉山を見ながら、石に溜まった水を持ち帰り習い事に使ったと言われている。

この日、「硯石」の水鏡には空色と木陰が揺れていた。
小説家であり詩人の「山田美妙(びみょう)」は著書の「戸隠山紀行」のなかでこう詠んでいる。

さらに遊歩道を進み「鏡池」へと向かいます。

この場所にどっしりと構えたように鎮座する大石がある。これが、

「硯石」
 「硯石」にはこんなお話が。
「硯石」にはこんなお話が。「鬼女紅葉(きじょもみじ)」の第一の家来「おまん」は剛力と健脚の女性で、荒倉山の合戦で紅葉と共に戦うが敗れてしまい敗走することになる。
そして平維茂(たいらのこれもち)らの追い手を振り切ってこの地まで逃げ切り、石にたまっていた雨水で血の付いた体を洗った。その時、この石に溜まった雨水が水鏡となり、そこに映った自分の姿があまりに恐ろしい鬼の形相だと知り、犯した罪の重さをを恥じる。
その後、中社勧修院で出家し、亡くなった方々を弔う日々の中、時にはこの場所で荒倉山を見ながら、石に溜まった水を持ち帰り習い事に使ったと言われている。

この日、「硯石」の水鏡には空色と木陰が揺れていた。
小説家であり詩人の「山田美妙(びみょう)」は著書の「戸隠山紀行」のなかでこう詠んでいる。
秋はまだ知らぬ深山の若もみじ いかなる風の色に染むらん

さらに遊歩道を進み「鏡池」へと向かいます。